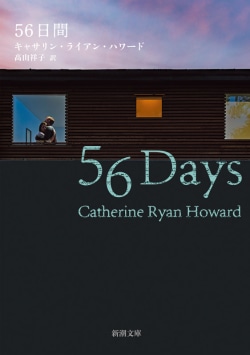『56日間』
- 著者
- キャサリン・R・ハワード [著]/髙山 祥子 [訳]
- 出版社
- 新潮社
- ジャンル
- 文学/外国文学小説
- ISBN
- 9784102402214
- 発売日
- 2022/09/28
- 価格
- 1,045円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
コロナ禍を背景にした企みに満ちた物語
[レビュアー] 吉田伸子(書評家)
アイルランド・コーク生まれの作家・キャサリン・ライアン・ハワードによるサスペンス小説『56日間』が刊行。新型コロナ禍で出会った男女の56日にわたる愛と悲劇を描いた本作の読みどころを、文芸評論家の吉田伸子さんが紹介する。
吉田伸子・評「コロナ禍を背景にした企みに満ちた物語」
なんて企みに満ちた物語なんだろう。
本書は二つのストーリーで成り立っている。現在である「今日」のパートと、タイトルにも使われている56日前を起点とする過去のパート。「今日」のパートで進んでいくのは、ある集合住宅で発見された遺体を巡る物語――遺体は誰なのか? 事故なのか、事件なのか? 死因は?――で、過去パートは男女の出会いとその別れに至るまでの物語だ。どちらも、背景には「コロナ禍」がある。
死体の話と恋愛の話が別々に進んでいくうえに、現在と過去が交互に、さらに恋愛の話では女性視点と男性視点、双方で語られていくので、軽く戸惑いながら読み始めたのだが、読み進めていくうちにその複雑さは全く気にならなくなる。まるで映画のカットバックのように、それぞれの場面が立ち上がってくるようになるのだ。そこからはもう、ぐいぐいと物語に引き込まれてしまう。
うまいな、と思うのは、現在、過去、それぞれの物語への導き方だ。現在パートでは、アイルランド警察の警部であるリー・リアダンと部下であるカール・コナリー巡査部長の登場のさせ方がとりわけ巧みだ。
金曜日の朝、リーが車を走らせているのは、カールを“救出”するためだ。出向いたのはカールの家で、彼は寝室で両手をベッドに手錠で繋がれていたのである。しかも素っ裸で(かろうじて下半身はフィット・シーツで覆われていたが)。
要するに、カールが見知らぬ女性とワン・ナイト・スタンドを楽しんだ“後始末”(手錠の鍵は女性によって捨てられてしまった)に、リーが駆けつけたのだ。カールの手錠を手荒く扱いながら、リーは尋ねる。「それで、彼女はどこにいるの? それは誰なの?」。「知るかよ。いろんな意味でな」と答えたカールに、リーは返す。「ロマンティックな気持ちになったことはあるの、カール?」
このシーンだけで、リーとカールの関係が浮かび上がってくる。女性の上司であるリーを、隙あらばセクハラまがいで揶揄しようとするカールと、1ミリの隙も見せず、返す刀で切りつけるリー。二人のこの、軽口の応酬、は全体的にアンダーなトーンで進む本書の中での、良いスパイスにもなっている。
「56日前」で始まる、過去パートの導入もいい。いわゆるボーイ・ミーツ・ガールのシーンなのだが、女性主人公のキアラ視点なので、ガール・ミーツ・ボーイと言うべきか。自分と同じように、〈テスコ〉というスーパーのセルフ・サービスのレジ・カウンターの行列に加わろうとしている男から、キアラは声をかけられる。「進んだら」と。男は、自分より先に行列に並ぶように譲ってくれたのだ。キアラは男がとても魅力的で、自分とは住んでいる世界が違うと察知する。けれど、店を出たキアラに、再び男は声をかけてくる。「いい袋だね」と。キアラのトートバッグには、スペースシャトルの絵がついていた。
そこからスペースシャトルの話になった二人は、オリヴァーと名乗った男からの提案でコーヒーを買いに行き、堤防に座って一緒に飲み、語り合う。時間が来て会社に戻るキアラに、オリヴァーは言う。月曜に、アポロ計画のドキュメンタリー映画を一緒に見に行かないか、と。
こうやって要約してしまうと、ごく普通の微笑ましくさえある男女の出会いのようなのだが、実際にはそうではない。いわく言い難い不安定さが、緊張感が、漂ってくるのだ。気にしなければそのうち飲み込んでしまえる程度ではあるものの、確かに喉に刺さっている小骨のように。うっすらとした、残り香のように。
その小骨に、残り香につられて読み進んだ先には何があるのか。キアラとオリヴァー、二人の関係はどうなっていくのか。そして、「今日」のパートで語られる、腐敗した遺体を巡る謎は? 二つのストーリーは、いつどこでどんなふうにリンクするのか。
途中、何度もページを遡り、“何が起きているのか”を確認しつつ読んでいったのだが、最後の最後の捻りには、思わず、えっ、と声が出そうになった。そしてその時、ようやく、作者が物語の中に張り巡らした細い糸の全てが見えてくる。そして、この物語が、コロナ禍の社会というかつてない背景を、あらゆる意味で生かしきったものであることも。
読み終えた瞬間、最初のページに戻って読み返したくなる一冊だ。