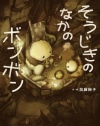『タイポグラフィ・ブギー・バック』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『タイポグラフィ・ブギー・バック ぼくらの書体クロニクル』正木香子著(平凡社)
[レビュアー] 金子拓(歴史学者・東京大教授)
書体から読み解く30年
読書委員を仰せつかり、様々な分野の書籍に目を通すようになって気づいたのは、本文で強調したい部分の書体を変えたり、傍線やマーカーを引いて目立たせたりする本が目につくことだった。傍線などは別だが、書体を変えるのは、マンガなどで浸透した手法だろう。本書ではこれを「多書体文化」と表現している。
著者は、最初の著書『文字の食卓』以来、本の重要な要素である書体(フォント)に注目し、言葉、文章、文学作品を書体という観点から読み解く刺激的な著作を発表している。同じ言葉、同じ文章でも、書体によってまったく異なる印象を与える。当たり前のようで、実は誰も真面目に考えてこなかった。著者の書体論は、言語表現論の新たな地平を切り開く画期的な仕事ではないかと思っている。
本書では、1990年代から2010年代までの30年間、活版から手動写植・電算写植を経てデジタルフォントによるDTPへと移る出版文化のなか、本や雑誌、マンガのセリフ、CDのジャケットや歌詞カード、テレビのテロップなどの書体に注目したエッセイ集である。幼い頃から「活字」が好きで、本や雑誌、マンガに触れてきた著者の実体験に裏打ちされた、相変わらずの示唆に富んだ洞察が随所に光っている。
メールやSNSの書体に見慣れてしまうと、「親しみやすく、伝わりやすい」「あかるさを損なわない、軽い言葉」が増えていくのでは、という指摘は意外に重い。文章や媒体に合わせて書体が選ばれるのとは逆に、書体により刷りこまれた言葉や文章が幅をきかせる世の中への違和感、というと、少し大げさすぎるだろうか。
以下は評者の世界の話。網野善彦氏・笠松宏至氏らの論文集の書体が、すぐれた日本史の論文を読んでいる気分を味わわせてくれた。網野氏の著作を別の書体で読むと何か違う気がした。海野弘『モダン都市東京』の元版も同じ書体であり(印刷は三陽社)、ずっと気になっている。