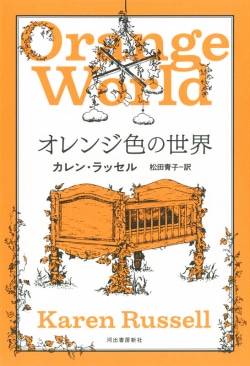『オレンジ色の世界』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
死と隣りあわせの世界
[レビュアー] 谷崎由依(作家・翻訳家)
妊娠していたときほど、死を間近に感じたことはない。命を身に宿しているのにおかしなことと思われるかもしれないが、わたしの感じていたのはその命の脆弱さだった。些細な(と普段であれば受け取れる)不注意によって損なわれ得る、まだこちら側のものではない命。生まれてからも同様、死なないようにと祈る日々だった。
著者の新生児育児中に着想された「オレンジ色の世界」を表題作とする本書に、死の色合いが強いのは、だから頷けることだ。
たとえば冒頭の「探鉱者」では、雪山のパーティーに招かれたふたりの若い女性が、誤って死者たちの集うロッジに迷い込んでしまう。ユーモラスでもある彼らとのやりとり。死者たちは異質なだけではなく、ゴールドラッシュに取り憑かれた父親を持つ女性たちには共感すら誘うところがある。
一方で「沼ガール/ラブストーリー」のキリアンにとって、沼地から発見されたミイラ少女は完全なる他者である。いや、彼女が意識を、意志と言葉を取り戻したとたん他者になったというべきか。お人形としか恋愛できない人間にとって、他者とは耐え難いものなのだろう。
死者と自身とが限りなく等価になっていくのが「ブラック・コルフ」だ。漆黒の森を抱く十七世紀のコルチュラ島には“死後医”が存在し、死者の膝腱を切ることで狼人間(ヴコドラク)になることを防ぐ。「ゴンドラ乗り」は大洪水に襲われた近未来か平行世界のフロリダが舞台だが、水に浸された廃墟に住む女たちはコウモリに似た能力を備えている。いずれも厚みのある描写が魅力的な二篇で、自然というものも死者たちの側にあるのかと考える。いやむしろ、人間であること、生きて理性を持つ存在であることのほうが、奇妙で例外的なのだろう。カレン・ラッセルの作品を読んでいると、そんな気持ちにさせられる。
妊娠出産とは、そうした正常運転の“人間”状態から逸脱する営みだ。「悪しき交配」の、ジョシュアツリーという木の種に寄生される状態は、つわりの時期のメタファーとしてもこのうえなく的を射ている。何かに寄生されながら、その何かを全身全霊で守ろうとすること。それは理性とかパステルカラーの“母性”なんていう言葉で説明できるものではない。
ここで表題作に戻るが、「オレンジ色の世界」とは、事故が起こってしまった後(赤色)でもなく、かといって安全(緑色)でもない世界だということだ。私事になるけれど、重度の切迫早産で赤子の命が心配されていたわたしも、ラエとおなじく機会があったら悪魔と契約していたかもしれない。と同時に添い乳地獄にも陥っていたので、夜な夜な母乳を飲ませる苦痛も身につまされる。
最後に「竜巻オークション」。本稿の文脈に収めきれなかったが、とても印象的だった。笑ってしまうような設定ながら、父親の役目を放って竜巻の崇高さに魅入られていく彼を、他人事として断罪できないし、笑い飛ばすこともできない。