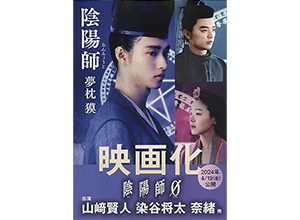草なぎ剛主演「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」社会の問題を全面に出した原作と、家族の物語に重心を移したドラマ 違いはあれど誠実な映像化!
推しが演じるあの役は、原作ではどんなふうに描かれてる? ドラマや映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回はろう者や中途失聴者の役者さんが多く出演したこのドラマだ!
■草なぎ剛・主演!「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」(NHK・2023)
-
- デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士
- 価格:814円(税込)
ああ、誠実な映像化だ──というのが第一印象だった。もちろん長編を前後編の単発ドラマに収めるために改編された部分はある。カットされたシーンも多いし、逆に原作にはない場面が加えられたりもしていた。けれど主要エピソードはいっさい省くことなく、たっぷり見せてくれるた。
主演の草なぎ剛さんや橋本愛さんらの芝居はもちろんだが、ろう者や中途失聴者を演じた役者さんたちの圧巻だったことといったら。このあたり、「あそこよかったね」「あれすごかったね」と語りたい気持ちが膨れ上がっているのだけれど、手話もできずろうの問題の当事者でもない私が安易に「わかったようなこと」を言うのも違う気がするので、ここでは私の専門である「小説」との関係に絞って語ります。ドラマでのろうや手話の描かれ方については、NHKの中の人や手話に詳しい人たちがさまざまな情報や分析をwebに載せてくれているので、ぜひそれらをお読みください。手話のわかる人が見ると、手話の意味と字幕の言葉が微妙に違う部分があって、そこにろう者と聴者両方への配慮が感じられるんですって! うわあ、そういうのがわかるといっそう楽しめるんだろうなあ。
ということで小説の話をしよう。原作は丸山正樹の同名小説『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』(文春文庫)。2011年に単行本が刊行されて以降、続編が3冊、スピンオフが2冊刊行されている著者の看板シリーズである。
主人公は荒井尚人、43歳(初登場時)。彼はそれまで事務職として勤めていた警察をある事情で辞めたあと、再就職先を探すがなかなか見つからない。仕方なく「特技」を活かして手話通訳士の資格を取る。彼が手話ができるのはコーダ(CODA:Children of Deaf Adults/聴こえない親を持つ聴こえる子ども)だからで、その生い立ちに複雑な感情を抱いていたため、本当はやりたくない仕事だったのだ。
それでも何件かの通訳を無事にこなした頃、荒井のもとに法廷通訳の依頼が舞い込んだ。窃盗未遂で起訴された被告がろう者だというのだ。その一件をきっかけに荒井は、ある殺人事件に巻き込まれることになる。それは荒井が前職でかかわった17年前の事件とも関係があるようで──というのが原作・ドラマに共通する導入部である。

イラスト・タテノカズヒロ
■社会の問題を前面に出した原作と、家族の物語に重心を移したドラマ
話の展開や事件の真相などは原作に忠実だし、冒頭に書いたように「誠実な映像化」なのは間違いない。ただ、「あ、そこ変えるんだ」と思った箇所があった。終盤、演出にかなり大きな(と私は感じた)違いがあったのだ。さらに原作にはない家族のシーンや法廷場面が加えられていたこともあり、社会的な問題を提言した原作に対してドラマは「家族の物語」に重きを置いたかな、という気がした。
その演出の大きな違いというのは、ある人物が手話で「過去の告白」をする場面。具体的に書くとネタバレになるのでぼかしておくが、その内容がとても衝撃的なもので、その場にいた人々は呆然とする──のだけれど。
この場面、ドラマでは声による言葉と手話が交互に展開され(同時ではなかったのは日本語対応手話ではなく日本手話だったからだろう。そのあたりはさすがに細やかだ)、その場にいたろう者も聴者も全員、告白の内容を理解しているという体裁になっている。しかし原作では、音声による言葉はない。ただ手話だけだ。手話がわかる人にしか告白の内容は伝わらない。だから手話がわかる人たちが慌てているのに対し、聴者たちは「何かこの場に相応しい話をしてるんだろう」とにこにこしているのである。
これは、ろう者と聴者の断絶の象徴だ。ろう者がどれほど手話で訴えても、聴者には聴こえない、聴者は勝手に話の中身を決めつけて勝手に納得しているということのメタファなのだ。そんなシーンをラスト間際に持ってきて、ろう者と聴者をつなぐ手話通訳士の荒井のある変化を描くのである。原作を読んで上手いなあと思ったところだったので、ここが変えられていたのは個人的には少し残念だった。ここはぜひ、原作で、その静かな告白を味わっていただきたい。
一方、感心した改編はそのあと、兄一家と荒井(と恋人一家)が、施設にいる母親に会いに行く場面。そこで、認知症を患う母親がずっとやっていた意味不明のジェスチャーの意味がわかるのだが、いやその真相がね! 上質なミステリかよ、と思ったさ。あの場面は原作にはなく、まるっとドラマオリジナルなのだが、映像でしかできない演出だ。手話のわかる人は途中で「もしかして?」と伏線に気づけたかもしれないし、真相がわかったときの「そういうことか!」というカタルシスも大きかったろうと思うと、羨ましいぞ。
また、窃盗未遂で逮捕されたろう者が老母に再会する一幕も、原作にはないドラマオリジナルだ。前述の荒井の家族の場面しかり、そういった感動的な家族エピソードを追加してきたのがドラマの特徴。その分、原作より感動路線になっていたが、原作者の丸山さんが本書に込めた思いはしっかり汲み上げられていたように思う。その思いとは、障害は「確かに特別なことではあるにせよ、それをマイナスのものでも逆に賞賛すべきことでもなく、障害を持たない人でも共感できるような種類の葛藤として描けないか」(著者あとがきより)ということだ。家族寄りのテーマにシフトしたのも「共感できるような種類の葛藤」を描くひとつの手法と言っていい。
■原作でろうと日本手話をもっと知る
そんなオリジナルエピソードを入れながらあの長編をどうやって尺に収めたのか。当然、削られた部分があるからだ。その削られた部分とはおもに、ろうや手話の現実を説明する「情報」の部分である。
本書はろうや手話通訳士という、多くの人にとって馴染みのない世界がモチーフになっている。その「情報の珍しさ」に読者はまず惹かれ、ここに描かれる「未知の現実」に驚くだろう。だが情報が知りたいならノンフィクションや学術書を読めばいいのであって、小説である必要はない。この『デフ・ヴォイス』という小説が素晴らしいのは、ろうや手話通訳のあれこれが有機的に物語と結びついてめちゃくちゃ面白いミステリになっているという点にある。
たとえばろう者が逮捕されたときの取り調べはどんな様子か。ろう教育とはどんなものか。ろう者はどんな不便を生活の中で抱えているのか。彼らのコミュニケーションの特徴はどこにある。そういった「情報」が、実は伏線になっていたり手がかりになったりする。実に上手いのである。そしてもちろん、物語とわかちがたく結びついているからこそ、ここに描かれるろうの現実が強く胸に残るのだ。
たとえば、手話に「日本手話」と「日本語対応手話」があることを私は本書で初めて知った。ドラマでは通訳依頼者の益岡老人が荒井との会話の中で、これまでの通訳は日本語に合わせた手話が多くて自分にとっては外国語のようなものだったが、荒井の手話は自分たちと同じ、と語る場面がある。手話にも種類がある、ということがさりげなく伝えられる場面だが、それがどういうものか、そして種類の異なる手話の存在が何を生み出しているかは原作に詳しい。また、私はこの稿で、ろう者、中途失聴者、聴者という言葉を使い、聴覚障害者・健聴者(健常者)という言葉は使っていない。その理由も小説を読めばおわかりいただけるはずだ。
この物語はろうの現実が描かれていることはもちろんだが、同時に「異文化の架け橋」の物語でもある。手話通訳士はろう文化(文化なんです。それも原作を読めばわかります)と聴者の文化をつなぐ架け橋だ。直接のコミュニケーションが難しくても、架け橋になる存在がいれば、そんな存在が増えれば、この社会はもっと暮らしやすくなる。それはろうに限らずあらゆる障害も同じだし、異なる国だったり文化圏だったり世代だったりも同じだ。私の仕事も小説と読者の架け橋でありたいと願っているが、さて、できてるかな?
おっと、推し活読書クラブなのに役者さんについて何も書いてない! つよぽんが素晴らしいのは論を俟たないが、荒井とその恋人のその後については続編『龍の耳を君に』『慟哭は聞こえない』『わたしのいないテーブルで』をお読みください。また、遠藤憲一さんが演じた刑事・何森稔が主人公のスピンオフもある。『刑事何森 孤高の相貌』『刑事何森 逃走の行先』(すべて創元推理文庫/東京創元社)の2冊だ。ぜひ彼らのその後を、つよぽんや橋本愛さん、エンケンさん、そしてドラマに出演したろう者の役者さんたちを思い浮かべながらお読みいただきたい。私は個人的に、中途失聴者で日本語対応手話と口話の使い手である片貝弁護士役の小川光彦さんのファンになってしまった。原作では「聴者のように明瞭な発音ではないが、聞き取りやすい言葉」を話すとある。もうイメージぴったりだったのよ!
大矢博子
書評家。著書に『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』(文春文庫)、『読み出したらとまらない! 女子ミステリーマストリード100』(日経文芸文庫)など。名古屋を拠点にラジオでのブックナビゲーターや読書会主催などの活動もしている。
連載記事
- 草なぎ剛主演「黄泉がえり」18年前の原作小説が今、心を打つわけ 2018/01/10
- 亀梨和也主演「ゲームの名は誘拐」ドラマには小説の続きがあった 逆転に次ぐ逆転で物語の印象ががらりと変わる 20年以上前が舞台でも時代設定に違和感なし 2024/07/17
- 高橋海人主演「95 キュウゴー」ドラマの映像✕小説の描写で解像度が一気に上がる! 90年代の青春を小説で味わう 2024/05/22
- 小芝風花・安田顕主演「天使の耳 交通警察の夜」単話ものをテクニカルな手法で再構成 30年前の原作は逆に新鮮に! 2024/04/24
- 奥智哉・青木崇高主演「十角館の殺人」なんだこの幸せな映像化は! 映像化不可能と言われたミステリの金字塔を見事にドラマ化 数少ない改変部分も原作ファンへの目配りがすごい 2024/04/17
- 「光る君へ」あのシーンに萌え死んだ! 史実と虚構の重ね合わせにワクワク ドラマをより楽しむために読むべき本とは? 2024/01/10
- 松村北斗、西畑大吾主演「ノッキンオン・ロックドドア」一話完結ミステリの背景にある大きな物語に注目 原作はゆっくり? ドラマはいきなり? 違いと楽しみ方を解説 2023/08/16
- 加藤シゲアキ出演「満天のゴール」単発ドラマじゃもったいない! シゲ演じる謎めいた医師の名シーンをぜひ原作で! 2023/07/26
- 菊池風磨出演「きよしこ」原作にはほとんど出てこない風磨くん演じる編集者の存在がキモ 「自分ではない人」を理解するということ 2023/07/12
- 重岡大毅主演「それってパクリじゃないですか?」しげちゃんのドSキャラにびっくり! 構成を大きく変えたドラマ版は原作未読・既読どちらでもワクワクに 2023/05/24