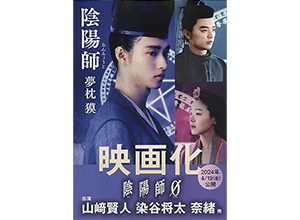加藤シゲアキ出演「夜がどれほど暗くても」週刊誌記者が追われる側に シゲ演じる記者の果たす役割とは
ノイズなんかに目もくれずに人をかき分け風のように駆け出す皆さん、こんにちは。ジャニーズ出演ドラマ/映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回はシゲ&辰巳くんのWOWOW初出演作となったこのドラマだ!
■加藤シゲアキ(NEWS)、辰巳雄大(ふぉ~ゆ~)・出演!「夜がどれほど暗くても」(2020年、WOWOW)
-
- 夜がどれほど暗くても
- 価格:770円(税込)
原作は中山七里の同名小説『夜がどれほど暗くても』(ハルキ文庫)。単行本の発売は2020年3月だったが、ドラマ化に併せて単行本からわずか7ヶ月で文庫化された。主演の上川隆也さんの写真が大きくあしらわれた全面帯(あれはカバーではなく大きな帯なので、はずすと本来のカバーが出てきます)が目印。
志賀倫成は大手週刊誌の副編集長。スキャンダル記事で売り上げを伸ばし、会社の屋台骨を支えているという自負があった。ところがある日、大学生の息子の健輔が、大学講師の星野希久子をストーキングした末に夫ともども殺害、自分もその場で自死したと警察から告げられる。これまで週刊誌の副編集長として追う側・叩く側だった志賀は、「ストーカー殺人犯の親」として追われる側、叩かれる側になってしまい……。
というのが原作・ドラマに共通する物語の導入部。原作では「週刊春潮」「春潮48」だった雑誌名がドラマでは「週刊時流」「月刊時流」に変更されていたり(いやこれ原作読むと笑っちゃうくらいモデルになった雑誌が露骨だからね)、原作の健輔は現場で死んでいたのに対しドラマでは死ぬまでに間があったりという僅かな違いはあるものの、全4回のうち第2回まではセリフなども含めて基本的に原作に忠実だった。
原作からの大きな改変があったのは第3回以降だ。原作では健輔が殺人犯であることはひとまず既定路線として進むが、ドラマでは早々に冤罪の可能性が持ち上がる。息子を信じたいという志賀の立場のみならず、警察内部からも疑いの声が出る。もちろんその過程で、追う側・叩く側だった志賀の立場が逆転する様子や、被害者の娘・奈々美との関係も原作通りに描かれるが、本当に健輔が犯人なのか、そうでないのなら真犯人は誰なのかというミステリがドラマの主筋だ。

イラスト・タテノカズヒロ
■視聴者の視点に寄り添うシゲの役どころ
シゲが演じる井波は「週刊時流」(原作では「週刊春潮」)の記者。ドラマでも原作でも冒頭に登場する。文芸志望だが週刊誌に配属され、担当した記事はアイドルの不倫。これを出せばこのアイドルは潰される。そんな記事に意義はあるのかと悩み、手が止まる。しかも井波はかねてよりそのアイドルのファンだった。そこを志賀から一喝される──。
そのあとで志賀が編集長の鳥飼と本音を語り合うくだりも含め、この冒頭は、原作・ドラマともに週刊誌記者の立場を表す、とても象徴的な場面だ。雑誌は売れてナンボであり、硬派な政治記事を載せた号より芸能人の不倫記事の方が売れるという現実がある。記者それぞれに思いや葛藤があったとしても、それに蓋をして「売れる記事」を書く。書く方が悪いのか買う方が悪いのかは、卵と鶏の議論と同じで出口がない。さらに管理職であれば、それこそ自分の本音に蓋をして部下に「記者の立場」を教える必要がある。
まあぶっちゃけジャニオタとしては──他のアイドルや芸能人のファンの皆さんもおそらくは同様だろうが──週刊誌には何とも言えない思いがあるわけで。私は仕事がら週刊誌に書評を寄稿する立場なので言えた義理ではないのだが、それでも(あるいは、だからこそ)物語冒頭の井波の言葉には強く首肯し、同時に志賀の言葉には反発を覚えたものだ。
おっと、ここでひとつ注意。ドラマ同様の井波の活躍を楽しみに文庫をめくる人もいるだろうが、原作では井波の出番はこの冒頭4ページだけなのである。そのあとは志賀と編集長の会話の中に名前がちょろっと出てくるだけ。だから伊波が志賀を取材したり、志賀と一緒に真相を追ったりするくだりは、完全にドラマオリジナルなのだ。だがここに意味がある。
物語の主人公は上川隆也演じる志賀だが、その環境は特殊だ。追う側から追われる側への転落は、読者(視聴者)にとっては「自業自得」と「辛い、可哀想」の両面を持つ。あまりにハードな彼の立場は、安易な共感を拒絶しつつ読者に「自分はどう感じるのか、何が正解なのか」という問いを突きつける主人公と言っていい。その問いを突きつけられる側にいるのが、シゲ演じる井波なのだ。
社会的意義を見出せないアイドルのスクープを正当化する上司への反発。その上司が叩かれる側に回ってマスコミから逃げようとしたとき、その自己矛盾を追及する姿。冤罪かもしれないという疑惑に対し、だとしたら自分の仕事は何なのかという迷い。ジャーナリズムとは何か、正しいことは何かと揺らぎ続ける井波の姿こそ、このハードなドラマにおいて視聴者が「下世話な記事は読みたくない」と「真相を知りたい」の間で揺れる自らを仮託できる存在なのである。
■シゲのいない原作を、「シゲならどうするか」で読んでみる
じゃあ井波が出てこないなら原作は読まなくてもいいかな──いや、待て待て。そうではない。だからこそ読んでほしい。
原作に井波という読者に近い立場の存在がいないのは、志賀の環境をダイレクトに読者に味わわせることが狙いだ。ドラマでは第3話から真犯人を探すというミステリ展開が中心となり、それにまつわるとある社会問題がクローズアップされたが、原作ではその要素は薄い(ないわけではないがあまり前面に出てこない)。なぜなら原作のキモは、加害者の父と被害者の娘が、「どちらも被害者」という立場でぶつかりあい、わかり合っていくくだりにあるからだ。
ドラマでも描かれたが、原作の志賀はドラマ以上に被害者の娘・奈々美の状態を慮る。自分が傷ついても、晒されても、彼女を守ろうとする。その動機は何か。それは二重の贖罪だ。息子が彼女の両親を殺したことに対する贖罪と、自分も携わってきた「報道」というものによる二次被害を受けたことへの贖罪。と同時に、志賀自身も過熱する報道により被害を受ける。志賀の視点で読むしかない原作では、それはとても辛く、同時にとても崇高な(悪く言えば綺麗事の)行動である。
だから原作を読むときに、そこに井波の視点を入れてみてほしいのである。これを井波ならどんな記事にするか。どんなスタンスで、何を読者に届けようとするか。ドラマを見た読者なら、そういう読み方が可能なはずだ。
シゲは新刊『オルタネート』(新潮社)の取材で新潮社を訪れた際、「週刊新潮」の編集部を見学したという。そこにいたのは「一般的なサラリーマンと変わらず、普通に仕事をされていた」人たちだったと彼は語っている。また、「週刊文春」の編集部を取材して書かれた大崎梢の小説『スクープのたまご』(文春文庫)でもやはり、そこにいるのは普通の人たちだという描写がある。
ジャニオタ、アイドルファンの身からは、時として敵視してしまう週刊誌。このハードな原作小説をシゲ演じる井波の目で読み返すことは、報道する側はもちろん、報道を「受ける側」のあり方についても考え直すいい機会だと思う。
おおっと、辰巳くんについて書くスペースがなくなった! ファンの皆さんすみません。辰巳くん演じた三田刑事は原作に登場しないオリジナル(もともと警察関係は脚色が多く、ほぼ原作とは別物だった)。出番は決して多くなかったしシゲとの絡みもなかったけれど、「監察医 朝顔」(2020年、フジ)に続いての刑事役、高嶋政伸や原田泰造といった曲者揃いの役者陣に一歩も引けを取らない様子は頼もしかった。できればもっと見たかったなあと思うあなた、原作にはドラマに登場しなかった葛城というナイスな刑事がいるので、ぜひ彼を辰巳くんでジャニ読みしてみて!
大矢博子
書評家。著書に「読み出したら止まらない!女子ミステリーマストリード100」など。小学生でフォーリーブスにハマったのを機に、ジャニーズを見つめ続けて40年。現在は嵐のニノ担。
連載記事
- 加藤シゲアキ出演「満天のゴール」単発ドラマじゃもったいない! シゲ演じる謎めいた医師の名シーンをぜひ原作で! 2023/07/26
- 井ノ原快彦・加藤シゲアキが銀行員役で共演!「シャイロックの子供たち」ジャニーズ先輩後輩のドラマ内関係に注目! 2022/11/02
- 加藤シゲアキから長尾謙杜へ リメイクドラマ「パパとムスメの7日間」の原作からの改変ポイントとオマージュを楽しむ 2022/10/05
- 加藤シゲアキ出演「剣樹抄~光圀公と俺~」シゲ初の時代劇は主人公の宿敵! 妖艶で非情な美形悪党はなぜ江戸を襲うのか? 原作から解説 2021/12/08
- 加藤シゲアキ出演「六畳間のピアノマン」と最新作『オルタネート』の共通点 2021/02/10
- 加藤シゲアキ主演「悪魔の手毬唄」散りばめられた「継承」に納得! 2019/12/25
- 加藤シゲアキ版「犬神家の一族」で実感 金田一とジャニーズ〈継承〉の魅力 2019/01/09
- 加藤シゲアキと中島裕翔が『ピンクとグレー』でシンクロする[ジャニ読みブックガイド第6回] 2017/08/02
- 増田貴久主演「レンタルなんもしない人」アイドルと「なんもしない人」はどちらも「触媒」だった 2020/05/13
- 増田貴久が「本に目覚めた!」 ドラマ「パレートの誤算」原作小説を今読むべき理由とは 2020/04/01