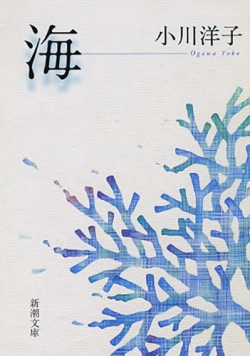桜色の道を歩みだすには

撮影:南沢奈央
2020年を取り戻した。今、そんな感覚になっている。
先日、今年に入って2本目の舞台公演を終えたが、2本とも昨年に上演する予定だったもので、コロナの影響で延期になった作品だった。緊急事態宣言下で、通常運転とはいかないまでも、今度は無事に初日と千秋楽を迎えられた。感謝の気持ち、そして安堵。
ようやく自分の中の2020年にピリオドを打てたところで、わたしの2021年はこれからいよいよ始まるぞ!と、次の作品に入るまでちょっと空くのに、やけに意気込んでいる。この読書日記がお正月ぶりの更新になってしまったが、今まさに、明けましておめでとうございます気分なのだ。……半分冗談としても、本当にこの半年間ほど時計を気にせずに走り続けてきたような状態だったから、もう桜が咲いているなんて信じられない。しばらくは感覚の調整が必要だろう。
-
- 海
- 価格:572円(税込)
どこか、何かが欠けていたからうまく進めなかったのか、と小川洋子さんの『海』を読んで気づいた。昨年からずっともやもやと引きずっていた、不安や居心地悪さ、ぎこちなさ、不安定さ――。それはきっと、わたしの中のどこか、何かが欠けてしまっていたからだ。
本の裏の紹介文に、「『今は失われてしまった何か』をずっと見続ける小川洋子の真髄」と書かれているが、「失われてしまった何か」というより、本書に描かれるものは「欠けてしまった何か」のほうがわたしにはしっくりきた。
医学部の大学院生から預かった論文の原稿をタイプ打ちする事務所での物語、「バタフライ和文タイプ事務所」の中で、主人公〈私〉から、壊れた睾丸の「睾」の字の活字を受け取った活字管理人がこんなことを言う。
〈「何ものにも惑わされず、真っすぐに、すくっと大地から立ち上がってくるような気高い作りをしていますが、同時に、ほんの少し爪で弾いただけで、ばらばらに崩れてしまいそうな、気弱さも隠しています」〉
睾の「幸」の部分の中央の二つの点のうち左側が、半分に欠けただけだったが、なるほど〈私〉にもその活字が〈それだけで著しくバランスを失って〉、〈うちひしがれ、縮こまり、みすぼらしく震えてい〉るように見えた。
この欠けた活字のような存在、それが本書の7篇の短編作品それぞれに出てくるのである。
婚約者の彼女の実家を訪ねた主人公と、彼女の“小さな弟”の一晩の交流を描いた表題作では、彼女の家族と彼女の関係や、父親の仕事、ボケ始めてしまったおばあちゃん、“小さな弟”、それぞれに何か少しだけ欠けていて違和感があり、どこにでもありそうな現実の中に“不均衡”や“ぎこちなさ”が描かれる。
その中に入った主人公も終始居心地が悪いわけで、さらに“小さな弟”と一緒の部屋で寝ることになり、気まずさを拭えない。だが、彼が寝る前に必ず見るという動物のドキュメンタリーや「鳴鱗琴」という自作の楽器を見せてくれたことによって、その欠けている部分が埋められていくようなのである。
「バタフライ和文タイプ事務所」でも描かれているように、登場する人物それぞれ、どこかみな気高さを感じる後ろには脆さも見え隠れする。だけど、全編を読み、さらに最後に収録された著者のインタビューを読んで思ったのは、欠けてしまった何かというのは、人との交流で埋められる、補える、もしくは欠けたままでも支え合えるということ。
観光ガイドをする母親を持つ〈僕〉と、〈題名屋〉という仕事をする老人の物語「ガイド」で、〈シャツ屋〉の小母さんの仕事ぶりを描写している場面があり、それがまさにそのことを表しているようだった。
〈不完全、と言いながら〉、〈緻密で洗練されていた〉。〈一枚の布が切り離され、縫い合わされ、少しずつシャツの形になってゆく〉——。
一人一人ではどこか不安定で、不格好かもしれなくても、誰かと合わされば心地よい安定したものになるかもしれないし、誰かと誰かを繋ぎ合わせてくれるような人もいるかもしれない。読後には、そんなやさしさやあたたかさを感じられる一冊だった。